兎男の夏休み [a r c h i v e s]
A・ピエール・ド・マンディアルグ 『オートバイ』
英国オルタナティヴ・シーンに疎遠な音楽ファンと雖も、The Pop GroupやJoy Divisionという奇妙な名称を持つ尖塔の前は素通り出来なかったはずだ。あるいは観光客が戸惑っている間に彼らの方が解体・消滅してしまったと言うべきかもしれない。風化する風景の中で失われてしまった2区劃だけが真空地帯のように殺傷し、蜃気楼のように来訪者を魅惑する。The Pop Groupは3つに分裂し、Joy DivisionはIan Curtisの極めて意志的な縊死によって解散を余儀なくされた‥‥なぁんてことは、今さら書くことさえ躊躇うほど有名な「伝説化」された物語に過ぎない。高速回転することで強烈なエナジーを放射するThe Pop Groupは拒絶し、挑発し、火傷させ、覚醒させたから1度充填するだけで長時間持続可能だったけれど、Joy Divisionは念仏のような反復ビート、いわゆる「ネクラ派」のプロトタイプと化しつある、ギターやシンセで裁断された夥しい薔薇色の肉片が漆黒の闇の中でスローモーションで乱舞する耽美的サウンドは、聴く者を安楽な、人肌の、腥い、催眠の「暗黒の小孔」へと誘い込む。
ポスト・パンク / ニュー・ウェーヴのバンドの1つ、Echo & The Bunnymenも霧の向こうにJoy Divisionの幻影が見え隠れしている。彼らの3rdアルバム《Porcupine》(Korova 1983)は2nd《Heaven Up Here》(1981)で完成したサウンドに、Shankerの双胴ヴァイオリン、木琴、竪琴?‥‥等のエスニックな効果音を重層的に象眼することで実験的な色彩を醸し出す。Doorsのヴォーカルを多分に意識したIan McCullochの自己陶酔と嫌悪を鼻腔から吐き出す押しつけがましさ、巧いのか下手なのか判らないWill Sergentのサイケデリックなギターと独特のリズム・リフ、角刈り兄さんの叩き出す奥行きのある深く沈んだドラム音、効果的なリズム・ボックスの使用‥‥。スピード感溢れる〈Back Of Love〉ではアグレッシヴに、典型的バニーメン調の〈Ripeness〉、タイトル曲〈ヤマアラシ〉の陰鬱なトーン、《just like my lower heaven, you know so well my higher hell...》とIan McCullochの多重唱する〈Higher Hell〉が、〈All My Colours〉や〈Over The Wall〉といった代表曲を彷彿させて素晴しい。
Joy Divisionを超えたとさえ評された2nd《Heaven Up Here》に収録されている〈All My Colours〉──Ian McCullochが「ジンボー、ジンボー、ジンボー、ジンボー‥‥」と執拗にリフレインすることから別名〈Zimbo〉と呼ばれている──は、アルジャナン・ブラックウッドの『ジンボー』(月刊ペン社 1979)との関連性も指摘された。もし兎男たちが非難されるとしたら、カッコ良すぎることくらいかもしれないと、4枚のアナログ盤のスリーヴ──《Crocodiles》(1980)、《Heaven Up Here》《Porcupine》《Ocean Rain》(1984)──に見蕩れながら考える。夜の森の中で強烈な光を浴びて樹木に凭れ掛かる兎男たち、夜明けの浅瀬で飛び交うカモメたちと共に佇む4人のバック・シルエット、凍結した渓谷(河・滝・崖)の辺りを散策するバニーメン、蒼い洞窟の入り江でボートに乗る彼ら‥‥。カメラマンのBrian Griffinとアート・デザインを担当するMartyn Atkinsって気になるな。Depeche Modeの「鎌振り農婦」も同じコンビだったし‥‥。
*
樹村みのりの作品であっても、例えば〈昇平クンとさちこサン〉や〈菜の花畑シリーズ〉に代表される比較的軽めの「こうふくな話」と、「雨の中のさけび」→「トミィ」→「解放の最初の日」→「メダリオン」→「パサジェルカ」と続くヘヴィーな系譜とでは自ずから読後感に差が認められるが、両者間の底流には「人間相互の理解は可能なのか?」という共通項が潜んでいる。人間相互のコミュミケート手段としての「言語」(特に話言葉)に対して作者は恐らく懐疑的なのだろう(不安だからこそ、矩形で囲ったナレーション形式を発明した?)。彼女にとって理想的な状態とは「言葉」を必要としない関係であるかのようにも思える。その最も美しい例が、幼いまあチャンと女子大生・森ちゃんの「せんそう」についての会話だった‥‥もりちゃんは答えることが出来ない‥‥ただ、まあちゃんを抱きしめるだけだ。「言葉」に呪縛された世界に棲む人々が「言葉」を超えた世界を希求するのは当然のことである。ところが厄介なことに、言葉のない世界はもう1つ存在するのだった。
「相手は私をどう思おうと考えようと、相手の自由なんです。ですから、誤解は解く術もありません」──欧州テロ爆破事件を扱った異色作「メダリオン」に続く中編作「パサジェルカ(女客船)」は、かつてナチス親衛隊を志願した女主人公リーザと囚人マルタのアウシュビッツ内での物語である。南米へ向かう客船へ(途中寄港した港から)乗船して来た人々の中にマルタと似た女性を発見したことから、恐怖と苦悩に満ちたリーザ(夫と旅行中)の回想が船上(現在)と同時進行する。ハーレーに跨がってアウトバーンを疾走するレベッカ・ニュルの「夢想」ほどエロティックでもエキサイティングでもないけれど、空間移動しながら時間遡行するアンネリーゼの孤独と絶望。神経症的な描線と痛々しい肉体。初期作品と比べ、方法も複雑化し、表現も深化したものの、禁欲的なまでに首尾一貫したテーマの掘り下げに驚かざるを得ない。
ラスト・シーンでリーザは相手に向けてマルタの名前を呼ぶが、曖昧な反応──微かに振り向く、まるで呼び声自体に誘惑されたように──しか得られないままにマルタ(?)は下船してしまう。ここでも「言葉」は失われて、人間相互のコミュニケーションは断絶したままだ。リーザは2重に幽閉される。彼女が船内に永久に軟禁され続けるように、忘れ去ろうとしていた忌わしい過去の記憶は未決着のまま宙吊りにされ、彼女の中で新たに胚胎する。近年の作品で圧倒的に多い(食傷するくらいだ!)のが、愛されなかった少女A、あるいは失恋した女性Bというパターンである。『ジョーン・Bの夏』(東京三世社 1983)に収められた3つの短篇(2作品が雑誌掲載時未完!)でも、そんな彼女たちの内面が外在的に描写されて行く。
夜の廃墟に出没する幻の少年ハインリッヒは、傷心の旅行者シンシア・クレイ(B)の内面の投影であるのと同時に、家族を救えなかったことを悔やむ少年の魂と失恋のショックから立ち直れなかったセシーの交感でもあった「夜の少年」。山岳病院へ画家として招かれた美大生・野沢伸子(A+B)は、幻覚=夢の中で少女期の彼女自身と対面することになったのだし、伸子の描いた壁画は等身大の自画像だった「水子の祭り」。そして表題作「ジョーン・Bの夏」において、その傾向は露骨なまでに露わとなる。女流作家エレイン・メイへの憧れと幻滅‥‥。女子高生ジョーン・B・アンダーソンに纏わりつき、常に彼女を反駁する自称「親友」のバーバラは、J・B(バーバラ)の「分身」だったのだ。最後に収録されている「ひとりと一匹の日々」は先に分類したライト・タイプの短篇で、猫好きの読者には堪らない小品になっている。
作者にとって対人関係の亀裂は内部分裂と同義であり、内と外との対立を信じない。《内部で起こることは外部でも起こる》。内面の葛藤は外界へ投影=外在化され、「他者」からは拒絶されてしまう。そして両者がコミュニケートしたと思えた瞬間、「他者」は主体に取り込まれて溶解する。見えないものを視てしまう彼女たちの「幽霊」や「分身」好みは方法論に留まるどころか、彼女の資質に深く根ざしたものなのである。ここまで付き合ってくれた賢明なる読者諸君ならば作者の考える「他者」とは一体何なのか?──「他者」が存在しないではないか!──と苦笑混じりに反論したくならないでしょうか。しかし、樹村みのりは「自己」が解放された(あるいは幽閉された)ところで俯瞰し、ペンを置く。
*
グリール・マーカス 「記号論とニュー・オーダー」
「記号論とニュー・オーダー」の中で、グリール・マーカス氏が興味深い指摘をしている。《ジョイ・ディヴィジョンという名前は、ナチが、女性の奴隷を備えておいた、強制収容所内の女郎屋に付けた名前だった》‥‥。樹村みのりの「メダリオン」というタイトルは内容にそぐわない。むしろ「パサジェルカ」の原題──ゾフィア・ポスムイシの原作『パサジェルカ(女船客)』(恒文社 1971)と未完の映画『パサジェルカ』が存在する──に相応しいのではないか。恐らく作者は「メダリオン」という題名で「パサジェルカ」を描こうとしたが、何かの事情で急遽、内容だけ差し換えたと想われる。もっとも単行本収録時に「パサジェルカ」は「マルタとリーザ」というタイトルに変更されてしまったが。
*
過去に書いた手書き原稿を加筆・改稿してUPするアーカイヴス・シリーズの第6弾です。今回はちょっとヘヴィかもしれません。表向きは「兎男たち」と「樹村みのり」。ハーレーに跨がってアウトバーンを疾走するレベッカ・ニュルを背景に、Joy Divisionと「パサジェルカ」でアウシュヴィッツの暗い過去を焙り出すという2重構造が上手く行ったかどうか(タイトルは「兎頭狗肉」かな?)。エコバニのオリジナル・アルバムは2003年にボーナス・トラック(別ヴァージョンやライヴ)を追加した結成25周年記念のリマスターCDが出ています。流行りの「紙ジャケ」や2枚組のデラックス・エディションではなく、オープン・タイプの紙ケースに包まれたジェル・ケース仕様(輸入盤)。『ジョーン・Bの夏』は絶版ですが、『カッコーの娘たち』(文庫版)に「夜の少年」が収録されているはずです。
*
- 次回は100回記念(100th Article Anniversary)だぴょん^^
- グリール・マーカス 「記号論とニュー・オーダー」を引用しました(2018-11-19)
*
summer vacation of bunnymen / sknynx / 099

- Artisut: Echo & the Bunnymen
- Label: Warner Music UK
- Date: 2004/01/27
- Media: Audio CD
- Songs: Going Up / Stars Are Stars / Pride / Monkeys / Crocodiles / Rescue / Villiers Terrace / Pictures On My Wall / All That Jazz / Happy Death Men / Do It Clean / Read It In Books / Simple Stuff / Villiers Terrace / Pictures On My Wall / All That Jazz / Happy Death Men / ...

- Artist: Echo & the Bunnymen
- Label: Warner Music UK
- Date: 2004/01/27
- Media: Audio CD
- Songs: Show Of Strength / With A Hip / Over The Wall / It Was A Pleasure / A Promise / Heaven Up Here / The Disease / All My Colours / No Dark Things / Turquoise Day / All I Want / Broke My Neck / Show Of Strength / The Disease / All I Want / Zimbo

- Artist: Echo & the Bunnymen
- Label: Warner Music UK
- Date: 2004/01/27
- Media: Audio CD
- Songs: The Cutter / The Back Of Love / My White Devil / Clay / Porcupine / Heads Will Roll / Ripeness / Higher Hell / Gods Will Be Gods / In Bluer Skies / Fuel / The Cutter / My White Devil / Porcupine / Ripeness / Gods Will Be Gods / Never Stop

- Artist: Echo & the Bunnymen
- Label: Warner Music UK
- Date: 2004/01/27
- Media:Audio CD
- Songs: Silver / Nocturnal Me / Crystal Days / The Yo-Yo Man / Thorn Of Crowns / The Killing Moon / Seven Seas / My Kingdom / Ocean Rain / Angels And Devils / All You Need Is Love / The Killing Moon / Stars Are Stars / Villiers Terrace / Silver / My Kingdom / Ocean Rain
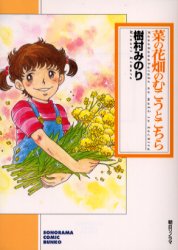
- 著者:樹村 みのり
- 出版社:朝日ソノラマ
- 発売日:2006/04/19
- メディア:文庫
- 収録作品:菜の花 / 菜の花畑のこちら側 / 菜の花畑のむこうとこちら / 菜の花畑は夜もすがら / 菜の花畑は満員御礼 / おとうと / わたしの宇宙人 / 結婚したい女 / ふたりが出会えば
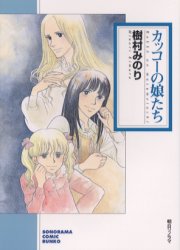
- 著者:樹村 みのり
- 出版社:朝日ソノラマ
- 発売日:2006/05/23
- メディア:文庫
- 収録作品:カッコーの娘たち / 40−0 / 晴れの日・雨の日・曇りの日 / 砂漠の王さま / 夜の少年 / Flight(飛行)


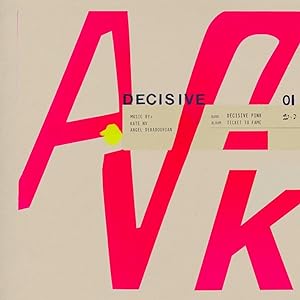
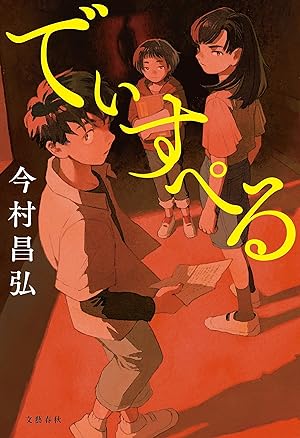
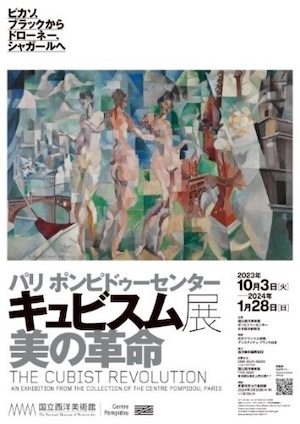

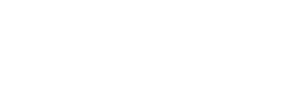



エコバニはこの季節に聴くと気温を微かに下げる効果がありますね。
ジャケットとアルバムの内容がシンクロした時の「ウォ!」っていう瞬間も好きです(私のお気に入りはOcean Rain)。
ただな〜、2年前にイアン&ウィルになってしまったエコバニ観たんだけど・・・あれは酷かった(号泣)
by yubeshi (2007-08-22 23:55)
yubeshiさん、コメントありがとう。
内容的には「兎男の冬休み」なんですが、
やんごとなき事情で「エコー&Bの夏」になりました^^;
エコバニの凋落(?)はJoy Divisionで行くかNew Order路線に転じるか
という迷いを払拭出来なかったことにあるのではないでしょうか。
Ian McCullochはRobert Smithのような天然ネクラ・キャラじゃなかった?
‥‥どの時代も新人は流行りの衣裳を纏って登場するものなのですが
(The PoliceもXTCもパンクだった!)。
《Ocean Rain》は日和った感じがなくもないけれど、
名曲〈The Killing Moon〉が入っているので許せちゃう^^
某メガストアのアクースティック・ライヴでも演奏していました(号泣)。
by sknys (2007-08-23 01:35)
菜の花の時期に樹村みのりの作品について書こうとして
菜の花スキンを作っていたらそこで力つきてしまいました^^;
(完全なる本末転倒)
うまく書けないんですよ…
当時、はやりの絵柄ではないのに彼女の作品に惹きつけられ
今でも私の中に根を下ろしているのを感じます。
ジョニ・ミッチェル、ニール・ヤングの名前を初めて知ったのは
彼女が書いたエッセイマンガを読んだときでした。
by miyuco (2007-08-27 12:58)
miyucoさん、コメントありがとう。
今からでも遅くないですよ。
「菜の花畑」のスキンと記事をUPして下さい。
書きかけの中途原稿でも良いじゃないですか(微力ながらサポートします)。
樹村みのりの雑誌掲載作品だって、
〆切りに間に合わず途中で力尽きた「未完」が少なくなかった。
少女マンガ家の誰にも似ていない絵、繊細な心理描写、深く重いテーマ
‥‥峠あかね(真崎・守)が、原作があるんじゃないかと疑ったほど、
最初から「樹村みのりの世界」は完成されていました。
by sknys (2007-08-27 20:38)